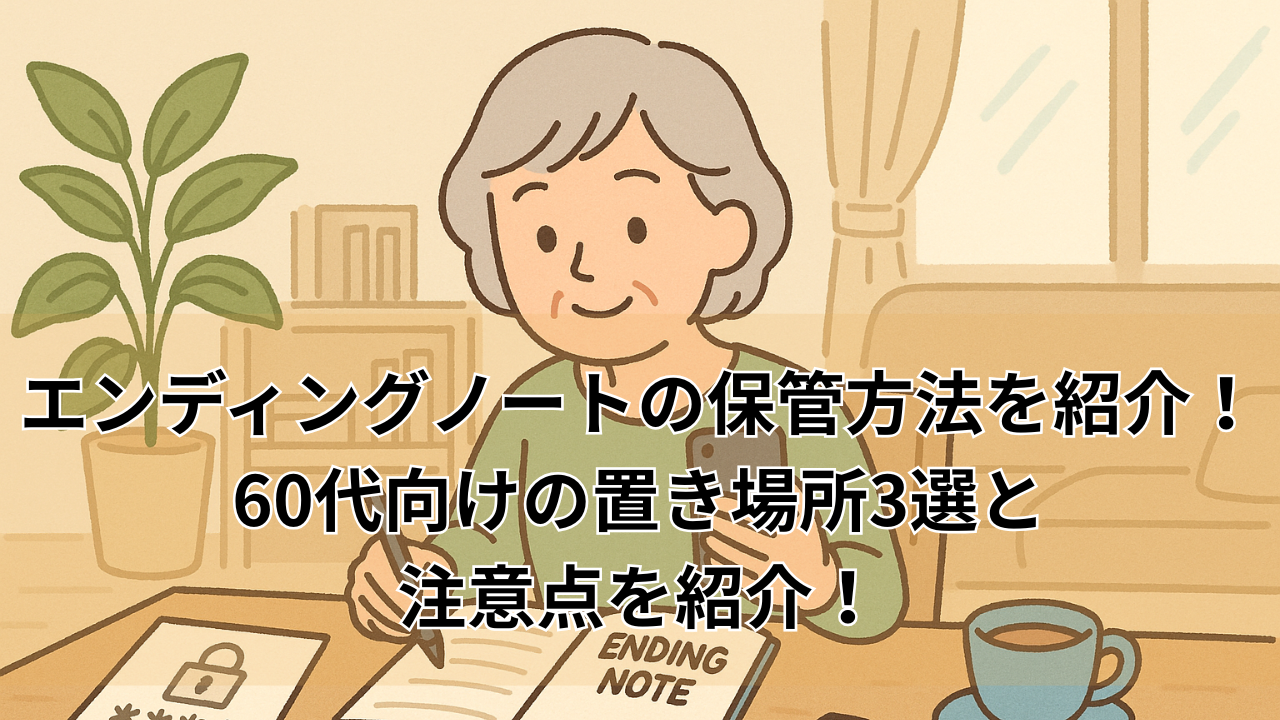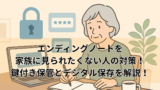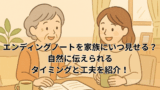エンディングノートを書いてみたものの、「これ、どこにしまえばいいのかしら?」と手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
家族に見つけてもらいやすく、でも見られすぎないようにしたい。
そんな60代のリアルな悩みに寄り添って、この記事ではエンディングノートの保管場所について具体的にご紹介していきます。
自宅の中のおすすめスポットから、補完方法まで、安心して取り入れられるアイデアをまとめました。
- 60代が選びやすいエンディングノートの保管場所
- 家族に伝わりやすい工夫と伝え方
- 貸金庫やデジタルで補完する方法
- プライバシーと見つけやすさを両立させるコツ
60代のエンディングノートの保管場所はどこが安全?
エンディングノートは書くだけでなく、保管場所もとても大切です。
せっかく書いたノートでも、いざという時に見つからなければ意味がありません。
60代の方にとっては、家族に見つけてもらいやすく、かつ安全な場所を選ぶことがポイントです。
ここでは、自宅での保管方法と、補完的な保管場所についてご紹介します。
家族がすぐ見つけられる自宅の保管場所3選
自宅で保管する場合は、「安全性」と「見つけやすさ」のバランスが大切です。
鍵付きの引き出しに入れても、鍵の場所が分からなければ見つけられないということも。
60代の暮らしに合った保管場所として、次のような選択肢があります。
- リビングの棚の引き出し(普段から家族も触れる場所)
- 寝室の机の上のケース(使い慣れた場所で視認性が高い)
- 冷蔵庫横のファイルボックス(生活動線上で意外と見つけやすい)
日常的に目にする場所に置いておくことで、「どこにあるか分からない」という事態を防ぎやすくなります。

私は、冷蔵庫の横にマグネット付きファイルを貼り、暮らしメモとしてノートを挟んでいます。家族にも「ここね」と言ってあるので安心です。
エンディングノートを貸金庫やデジタルコピーで補完する選択肢
「火災や水害が心配」
「見られたくない内容もある」
という方には、自宅保管だけでなく補完策の併用もおすすめです。
たとえば、貸金庫やデジタルコピーを活用すれば、いざというときの情報の消失を防ぎやすくなります。
貸金庫にオリジナルを入れ、自宅にはコピーを置く。
あるいは、スマホで撮影して画像をUSBメモリに保存しておくなども一つの方法です。
- 貸金庫に本体、自宅にコピー
- 自宅に保管、USBやクラウドに写真データ
- 2冊作ってそれぞれ別の場所に保管
どれか1つに絞るよりも、リスク分散のために複数の保管方法を組み合わせるのが安心です。
ただし、どこに保管したか家族に伝えることも忘れずに。
エンディングノートの保管場所に迷いやすい理由
エンディングノートの保管場所を決めようとしたとき、「どこが正解か分からない」と悩んでしまう方は少なくありません。
60代で初めて書く場合には、なおさら不安もあるものです。
ここでは、保管場所選びが難しく感じる理由を見ていきます。
紛失や盗難・災害リスクと家族が見つけられない不安
まず多くの方が心配するのが、
「なくしてしまうのでは」
「誰かに見られるのでは」
という不安です。
せっかく書いたノートが、火事や水害などで消失してしまうことも考えられます。
また、大事にしまいすぎて家族が気づけないというケースも実際によくあります。
特に60代では「とりあえず机の奥へ」という感覚でしまいこみ、そのまま忘れてしまうことも。
- 「金庫に入れたが鍵を伝えていなかった」
- 「タンスの奥に入れて家族が気づけなかった」
- 「防災意識で別の建物に保管して見つけられなかった」
保管の目的は「家族に必要なときに読んでもらうこと」。その視点で場所を選ぶことが大切です。

私は昔、重要な書類を押し入れの天袋にしまっていたのを忘れていて、娘に「どこにあるの?」と慌てて探したことがあります。
見られたくない情報をどう守るかという60代ならではの課題
エンディングノートには、人に見られたくない気持ちや暮らしの細かな情報を書くこともあります。
たとえば、趣味のこと、お気に入りのお店、日記のようなメモなど。
そうした内容を家族に伝えるのは抵抗があるけれど、いざという時には知っておいてほしい。
そんな思いから、保管場所に悩んでしまう方も多いです。
このような場合は、
「分けて保管する」
「目立たないように記載する」
といった工夫で、プライバシーを守りながら残すことができます。

私は家計のメモだけ別のノートにして、エンディングノートの最後に「生活費の記録は引き出しの封筒にあります」と一言添えました。
プライバシーを守りながら残すための方法は、他にもいくつかあります。
鍵付きやデジタルを活用した保管法についてはこちらでご紹介しています。
エンディングノートの保管方法と置き場所を決める具体的手順
保管場所を選ぶ際は、「とりあえずここでいいか」ではなく、いくつかの視点から自分に合った方法を見つけることがポイントです。
ここでは、自宅での置き場所を決めるときのコツと、補完策を取り入れた管理方法をご紹介します。
自宅でのおすすめ保管方法と注意すべきポイント
まずは、普段の生活動線の中で無理なく管理できる場所を選ぶことが大切です。
たとえば、郵便物や日用品などをまとめている棚やファイルケースなど。
ただし、目立ちすぎる場所だと、プライバシーが気になるという方もいらっしゃいます。
その場合は、「暮らしのメモ」と書いたファイルにして、他の書類と一緒に保管しておくと違和感がありません。
- 火気や湿気の多い場所は避ける
- 鍵が必要な保管場所は家族に場所を伝える
- 毎年見直す予定がある場所に置くと更新しやすい
保管場所は「大切にしすぎない」ほうが、実は見つけやすく、扱いやすいものになります。

私は、レシピノートや通帳と同じ引き出しに置いていて、娘にも「この中ね」とだけ伝えてあります。
貸金庫やデジタルコピーを組み合わせて二重管理する方法
保管に対する不安がある方は、リスクを分散させる二重管理がおすすめです。
たとえば、貸金庫にオリジナルを、自宅にコピーを置くというスタイル。
また、ノートをスマホで撮影し、パスワード付きUSBやクラウドに保存する方法もあります。
デジタル保存に慣れていない方は、家族にだけ画像を送っておくという形でも十分です。
おすすめの二重管理パターン
| 管理方法 | メリット |
|---|---|
| 自宅+コピー | すぐ取り出せて、災害時も安心 |
| 貸金庫+メモ | 安全性が高く、重要な項目だけまとめて保管可能 |
| 紙+写真データ | 手書き+スマホ管理で両方使える |
どこに何があるかを自分だけが知っている状態にしないことが大切です。
あくまで「家族が探しやすいようにする」という視点で組み合わせましょう。
家族にエンディングノートの保管場所を伝える工夫
どんなに工夫して保管していても、家族がその存在や場所を知らなければ意味がありません。
特に60代のうちは、「まだ元気だから」と伝えるタイミングを逃してしまいがちです。
ここでは、家族に安心してノートの場所を伝える方法をまとめました。
保管場所を一言だけでも伝えておく重要性
「あとでまとめて伝えよう」と思っているうちに、肝心な情報が伝わらないこともあります。
大げさに説明する必要はなく、「あの引き出しに入れてあるからね」と一言添えるだけでも十分です。
エンディングノートの内容までは伝えなくても、保管場所とノートの存在を知っておいてもらうことが大切です。
メモやふせんに「暮らしメモ」と書いて貼っておくだけでも、家族は探しやすくなります。

私は娘に「通帳の入ってる引き出しに、暮らしのノートも入れてあるよ」とだけ伝えました。中身までは話していませんが、安心感があるようです。
保管場所を伝えるときは、自然なタイミングや言葉選びも大切です。
その工夫や事例はこちらで解説しています。
見つけやすさとプライバシーを両立させる伝え方
「見られたくないけど、見つけてほしい」という気持ちのバランスは、60代ならではの課題です。
この場合、ノートを二層に分けるのも一つの方法です。
たとえば、日常の暮らしメモは目に入りやすい場所に、気持ちに関するページは別の場所に保管するなど。
また、「開けるのは必要になったときでいいよ」と前置きをしておくと、家族も心構えができて安心です。
- 「生活情報だけのノート」はリビングやキッチンに
- 「心の手紙」は封筒に入れて別の引き出しへ
- 「暮らしメモ」とラベルを書いたファイルで目立たせる
すべてを一度に伝えようとしなくても、「ここにあるよ」と言える範囲から始めるのが続けるコツです。
まとめ:エンディングノートの保管場所は安全性と見つけやすさの両立が大切
エンディングノートは、ただ「しまっておく」ものではありません。
家族が必要なときに迷わず見つけられるようにしておくことが、本当の意味での備えになります。
ここでは、60代の方に特におすすめしたい保管の工夫を改めてまとめます。
60代は自宅+補完策で二重管理を意識する
災害や紛失への備えとして、自宅と補完先の二重保管をしておくと安心です。
どちらか一方が見つからなくなっても、もう片方から情報を補うことができます。
二重管理といっても難しく考える必要はありません。
紙とデジタル、コピーと原本など、自分に合った方法でバランスをとればOKです。
- 自宅:生活動線上で目に入りやすい場所に保管
- 補完:貸金庫や写真データなどでバックアップ
- 家族に「ここにあるよ」と一言伝える
書いた内容が活かされるかどうかは、「どこにあるか分かるかどうか」にかかっています。

私は紙のノートを引き出しに、スマホで写真を撮ってクラウドにも保存しています。娘にも「どちらか見ればわかるよ」と伝えています。
家族が迷わない仕組みをつくることがエンディングノート活用の鍵
エンディングノートの内容がどれだけ丁寧でも、家族が存在を知らなければ活用されないのが現実です。
そのため、ノートを「家族が迷わず見つけて読める」仕組みにしておくことが大切です。
伝えるタイミングは、ふとした日常の会話の中で構いません。
暮らしの中の延長線上にある備えとして、無理なく自然に伝えていけるといいですね。
保管場所を工夫することは、エンディングノートを「形にする」最後の仕上げです。