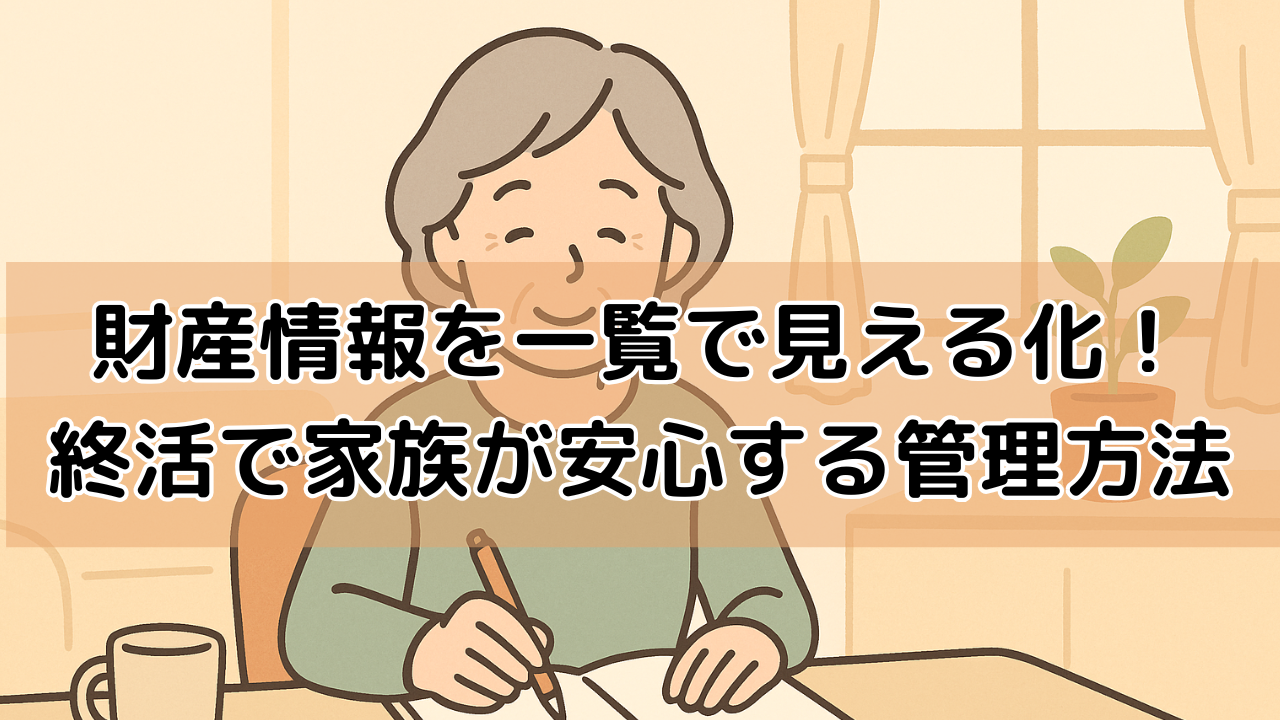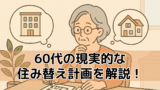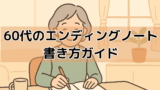「私に何かあったとき、娘が困らないようにしたい。」
そんな思いから、私は60代に入って本格的に終活を始めました。
中でも重要だと痛感したのが、財産情報の「見える化」です。
銀行口座、保険、年金、株式、不動産、デジタル資産。
これらの情報を整理しておかないと、残された家族は手続きのたびに大変な思いをします。
今回は、私が実践してきた財産整理の方法を、実体験を交えてお話しします。
60代の私が終活の資産整理で通帳13冊を3冊に減らした理由!
皆さんは、銀行口座や証券口座の通帳が何冊ありますか?
私の場合、終活を意識し始めたとき、家の中から出てきた通帳はなんと13冊。
夫の分、昔の職場でもらった給料振込口座、旅行積立、定期預金。
気づけば、もう使っていない口座が半分以上を占めていたのです。
これを整理しないまま残していたら、もし私が倒れたとき、娘はどれが今使っている口座か分からず、探し回ることになっていたでしょう。
この気づきが、私に「整理しよう」と思わせたきっかけでした。
家族が相続時に探した書類56枚の苦い体験
実は、私が終活を始めるきっかけになったのは、最愛の夫が亡くなった後の体験です。
夫が亡くなった後、役所、銀行、保険会社への手続きのために、必要な書類を探し回りました。
通帳、保険証券、年金の書類、株式の残高報告書、印鑑証明……。
その数、数えてみれば56枚以上。
「こんなところにあったのか!」と驚くような場所からも出てきて、毎日が宝探し状態でした。
悲しみと疲労が重なって、心身ともにボロボロ。
だからこそ、私は自分の財産情報は生きているうちに整理し、分かりやすくまとめようと決めたのです。
財産情報見える化で税理士費用を10万円節約
整理を進めていくと、もう一つの大きなメリットに気づきました。
それは、相続税の申告や相談の際に、税理士さんに払う時間単価が減ることです。
「何がどこにあるか」「評価額はどれくらいか」が整理されていれば、税理士さんの調査作業がぐっと少なくなります。
実際、私が試算してもらったとき、財産一覧をきちんと作成して提出したおかげで、相談料が約10万円安く済みました。
事前整理は、家族だけでなくお財布にも優しいのだと実感しました。
子供へ引き継ぐタイムライン作成の経緯
「いざというときの手順」を、私は娘に分かりやすく残すことにしました。
手紙のような形で、何から始めればいいか、どこに何が保管されているか、順番に書き出したのです。
これは私自身が夫のときに「何を先に動けばいいの?」と困った経験からです。
娘が慌てないよう、タイムラインを整理して渡す。
それは私なりの、娘への最後の思いやりだと思っています。
リビングテーブルで財産一覧を作る3ステップ
「忙しいし面倒そう……」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、財産の一覧作りは思ったより簡単です。
私が実践したのは、リビングテーブルの上で集中して行う方法でした。
難しいソフトも専門知識もいりません。
ここでは、私が実際にやった3ステップを紹介します。
金融書類を箱ごと並べる視覚化テクニック
まず、家にある金融関係の書類をひとまとめにして、リビングのテーブルに広げます。
私の場合、段ボール箱2つ分が出てきました。
通帳、残高通知、保険証券、年金通知……。
一つ一つ開いて確認するのではなく、まずは「見える化」することが大切です。
一度に全体を俯瞰できると、整理の流れがスムーズになります。
付箋と色ペンで優先度を即判定
次に、各書類に付箋を貼り、色ペンでマークをつけました。
私が使った色分けは、「現在使っている(赤)」「不要・解約予定(青)」「要確認(黄色)」の3色。
これだけで、何を優先すべきかが一目で分かります。
実際、使っていない古い通帳は、すぐに解約手続きを進められました。
評価額を概算するスマホ電卓活用
最後に、それぞれの残高や評価額をざっくり計算しました。
スマホの電卓アプリを使い、合計額を出すだけでも全体像が見えてきます。
「ああ、思ったより資産は多いけれど、ほとんどは現金ではないな……」と気づき、今後の対策も立てやすくなりました。
終活に必須の資産管理表項目とサブ資産α
いざ財産一覧を作ろうとすると、「何を書き出せばいいの?」と悩む方も多いと思います。
私も最初はそうでした。
ですが、一度テンプレートを決めてしまえば、とてもスムーズに進みます。

ここでは、私がまとめた資産管理表の主要項目と、意外と忘れがちなサブ資産をご紹介します。
銀行口座証券口座年金情報の整理順序
まずは、基本中の基本から。
銀行口座、証券口座、年金情報は、最優先で整理します。
一覧表では、金融機関名、支店名、口座番号、残高、種類(普通・定期など)を記入。
証券の場合は保有銘柄と評価額、年金は種類(国民年金・厚生年金・企業年金など)を書き出しました。
保険契約と受取人を一目で確認する欄
次に重要なのは、保険関係です。
保険会社名、契約番号、保障内容、満期日、そして忘れてはいけないのが受取人の名前。
私の場合、古い保険の受取人が夫のままになっていたものもあり、慌てて見直しました。
ぜひこの欄は丁寧に確認してください。
不動産とローンを紐付けるリンク欄
不動産をお持ちの方は、所在地、面積、評価額、登記情報をまとめましょう。
さらにローンが残っている場合は、その内容も紐付けておくと家族が後々助かります。
私も住宅ローン完済証明書を探すのに一苦労しましたので、早めの準備がおすすめです。
不動産の整理は、将来の住み替えも視野に入れるとより現実的になります。
住み替えの選択肢と判断基準を知りたい方は下の記事もどうぞ。
デジタル資産と貴金属をまとめるチェック欄
意外と盲点なのが、デジタル資産と貴金属。
ネットバンキング、電子マネー、ポイント、暗号資産など、オンラインで管理しているものはログイン情報ごと記録が必要です。
また、指輪や貴金属など、現物資産もまとめておくと良いです。
私は宝石箱の中の指輪を写真で残し、リスト化しました。
資産管理表テンプレート:手書き用とGoogleスプレッドシート活用
「パソコンが苦手で、Excelなんて使えないわ」という方も多いでしょう。
私もそうでした。
ですが、安心してください。
資産管理表は、手書きでも十分です。
※資産管理表を使う前に、エンディングノート全体の構成を知っておくと、書くべき内容の整理がしやすくなりますよ。
ここでは、私が使ってみたテンプレートをご紹介します。
手書き資産管理表:A4一枚版とバインダー版の特徴比較
手書き用テンプレートには、NPO法人や相続関連のサイトで配布されている無料テンプレートがあります。
ダウンロードしてA4に印刷でき、項目がシンプルで使いやすくなっています。
市区町村の窓口、地域包括支援センター、JA、信託銀行などで配布されているものもあり、冊子型が多く、高齢者でも書きやすい設計になっています。
A4一枚版の良いところは、全体を一目で確認できることです。
主要な口座、保険、不動産、重要情報をギュッとまとめ、冷蔵庫の裏や書類ファイルに貼っておけます。
一方、バインダー版は項目ごとに詳しく書けるため、情報量が多い方におすすめ。
私は最初A4一枚で整理し、後からバインダー版に移行しました。
Googleスプレッドシート版の共有設定
もし「少しはデジタル管理してみようかな」と思える方は、Googleスプレッドシートを使うのも手です。
オンラインで更新でき、家族と共有設定をすれば、離れて暮らす子供とも情報を分け合えます。
私は娘と「閲覧のみ」の設定で共有し、必要に応じてパスワードを教える形にしています。
こうしておけば、何かあったときでも安心です。
財産一覧を年1回更新保管する仕組み4手順
資産管理表を一度作ったら、それで終わり……ではありません。
私自身、毎年少しずつ状況が変わっていくのを実感しました。
私は、年に一度の見直しをしています。
ここでは、私が実践している年1回の更新・保管の方法を4つの手順でお伝えします。
誕生日リマインドをスマホアラームに登録
まず、「見直し日」を決めます。
私の場合は自分の誕生日にしています。
スマホのカレンダーやアラームに「資産管理表の更新」と登録しておけば、毎年忘れずに済みます。
誕生日は自分に向き合う特別な日なので、気持ちの区切りにもぴったりです。
紙USBクラウド三重バックアップ方法
次にバックアップ。
私は紙の原本を1部、USBメモリに保存したデータを1部、そしてGoogleドライブなどクラウド上に1部、と三重に保存しています。

どれか1つがなくなっても、他でカバーできるようにしています。
これは防災の観点からも重要です。
信頼できる家族と専門家への閲覧権限
大事な情報は、一人で抱え込まないことも大切です。
私は娘と、必要に応じてお世話になっている税理士さんに情報の存在を伝えています。
ただし、すぐにすべてを明かすのではなく、「必要なときに渡す予定のもの」として説明しておくのが安心です。
災害時持ち出し袋へ縮刷コピーを封入
最後に、防災の備えとして、資産管理表の縮小コピーを作成し、持ち出し袋に入れています。
これは万一の災害時に、避難先からでも最低限の情報を確認できるようにするためです。
私の場合、免許証や保険証のコピーと一緒にまとめて保管しています。
まとめ:子供に残す財産情報見える化7日間ステップ
ここまで、私が実践してきた財産情報の整理方法をご紹介してきました。
最初は面倒に感じるかもしれません。
ですが、一歩ずつ進めれば、必ず「やっておいてよかった」と思える日がきます。
何より、残される家族が安心できるというのは、私にとって大きな心の支えになりました。
「何から始めればいいのか分からない」という方のために、無理なく進められる7日間のステップをご紹介します。
7日間で進める!財産情報見える化ステップ
| 日数 | ステップ内容 | 具体的にやること |
|---|---|---|
| 1日目 | 書類の全出し&視覚化 | 家中の通帳・保険証券・年金通知などを段ボールや箱にまとめ、 リビングテーブルに広げて全体を「見える化」する。 |
| 2日目 | 色分けで仕分け&優先度チェック | 付箋や色ペンで「現役(赤)」「解約予定(青)」「要確認(黄)」に分類。 仕分けが視覚的に分かりやすくなる。 |
| 3日目 | 資産管理表に主要口座・保険情報を記入 | 手書きまたはテンプレートに、 銀行口座・証券・保険情報を記録。受取人の見直しも。 |
| 4日目 | 不動産・ローン・年金の整理 | 不動産の登記情報、ローンの残債情報、 年金の種類と受給内容を整理して記入。 |
| 5日目 | デジタル資産と貴金属のリスト化 | ネットバンキング、暗号資産、電子マネーなどの情報とログイン情報をまとめる。 指輪などの貴金属も写真付きでリスト化。 |
| 6日目 | タイムラインと伝言メモを作成 | 「もしものとき」の行動手順を時系列でまとめる。 手紙のような形にすると家族に気持ちも伝えやすい。 |
| 7日目 | 保管・バックアップ&更新の仕組み化 | 紙・USB・クラウドに三重保存。 誕生日などに見直す日を決め、 災害時の持ち出し袋にも縮小版を保存。 |
完了後に追加したい資産追記欄
そして、財産情報の整理は一度終わっても、後から新しい資産が増えることもあります。
そのため、私は管理表の最後に「追記欄」を用意しています。
新しく契約した保険や、最近始めたネット証券の情報など、小さなことでも書き足せるスペースを用意しておくと便利です。
「これで安心」と思える形を、ぜひ皆さんも一緒に作っていきましょう。