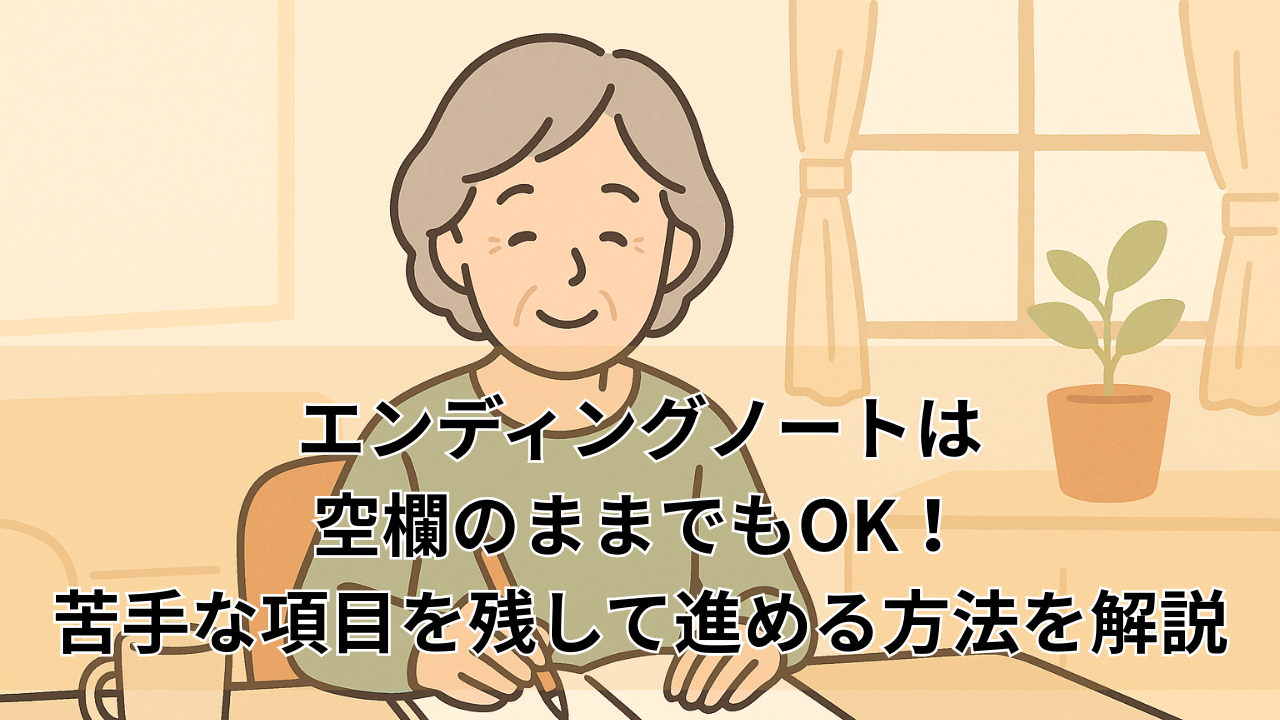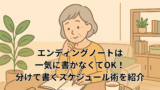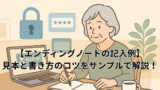「このページ、空欄のままでいいの?」
エンディングノートを書き始めたものの、苦手な項目に手が止まってしまう。
それ、あなただけではありません。
エンディングノートは、全項目を完璧に埋めるためのものではなく、家族に気持ちや情報を“伝える手段”です。
空欄があっても、きちんと伝えるコツを知っていれば安心して続けられます。
- 空欄のままでも伝わるノートの書き方
- 家族に安心感を与える注釈の工夫
- 苦手な項目を後回しにする方法
- 別紙メモや補足カードの活用アイデア
エンディングノートは空欄のままでも残せる!無理なく進める基本の考え方
エンディングノートに取り組もうと思ったとき、「全部きちんと書かなくちゃ」と思うと、手が止まってしまうことがあります。
でも実は、エンディングノートは空欄があってもまったく問題ありません。
苦手なところや決めきれないところは、無理に書かずに残しておいて大丈夫なのです。
あとからゆっくり考えたり、別の方法で伝えたりする工夫があれば、十分に家族に気持ちは伝わります。
苦手な項目を飛ばしても家族に伝わる注釈の付け方
どうしても手が止まってしまうような項目があったら、無理に書かずにそのままにしてOKです。
ただし、空欄のままだと「書き忘れたのかな?」と家族が迷うこともあるので、一言だけ注釈をつけると安心感が増します。
たとえば、
「まだ決めていません」
「保留中です」
といった簡単なメッセージを横に添えるだけで、意図がしっかり伝わります。
私も以前、書きにくかった「連絡先リスト」の項目に「今は手元にないので、あとで記入予定」とメモを添えておきました。
娘たちから「何か事情があるのだと分かって助かった」と言われたのを覚えています。

最初は注釈なんて面倒かなと思っていましたが、「ここはあえて空欄」と伝えることで、逆に丁寧な印象になるのだと気づきました。
後から書き足せるように別紙メモや補足カードを活用する
エンディングノートの項目が多すぎて書ききれない場合は、無理に一気に埋めようとせず、別の紙を使って情報を残しておく方法もおすすめです。
たとえば、ノートに「この内容は別紙に記載」と書き、別の紙にまとめておけば、空欄があっても家族はすぐに情報を探せます。
市販の名刺サイズのカードに要点を書いて貼っておく、メモ帳の切れ端を挟んでおくなど、身近なアイテムを活用すれば負担はぐっと軽くなります。
私の場合、ペットの情報は細かく書くのが面倒だったので、小さなメモカードに
- 動物病院の名前
- 連絡先
- 好きなおやつ
だけ書いて貼りました。
娘が「これで十分わかるよ」と言ってくれたのが励みになりました。
- Wi-Fiのパスワード
- ペットのお世話メモ
- よく利用するサービスやアプリの情報
- 配達・宅配の停止連絡先
このように、空欄を無理に埋めようとせず、メモやカードで補えば、自然とノートが仕上がっていきます。
エンディングノートに空欄を残してよい2つの理由
エンディングノートを前にして、「すべてきちんと書かなくては」と気負ってしまう方も多いのではないでしょうか。
でも実際には、空欄があっても十分意味があるのです。
ここでは、空欄を残しても大丈夫な理由を2つご紹介します。
完璧を目指すと書き進められない60代が多い背景
60代に入ると、健康のことや今後の暮らしについて漠然とした不安が増えるものです。
そんな中、エンディングノートに向き合うと
「きちんと全部書かなきゃ」
「間違えちゃいけない」
と構えてしまい、なかなか進まなくなってしまう方もいます。
実際、私も市販のノートを買ったとき、最初の1ページで手が止まりました。
専門的な言葉や選択肢が並んでいて、「これは私には無理かも…」と思ってしまったのです。
空欄を許すことで、プレッシャーが減り、自然と手が動くようになります。

最初は「ちゃんと全部書かなきゃ」と思っていましたが、「書けるところだけでいい」と思えたとき、気持ちがふっと軽くなりました。
暮らし情報を優先して書けば家族が困らない
エンディングノートの中でも、暮らしの中で必要になる情報は、意外と身近なことばかりです。
たとえば、冷蔵庫に何を常備しているか、家の鍵の置き場所、毎月届く宅配便の会社など。
こうした情報が残っているだけでも、家族にとっては大きな手がかりになります。
難しい項目よりも、こうした日常の情報を優先して書いていけば、たとえ空欄があってもノートの役割は果たせます。
- 合鍵の保管場所と数
- 宅配や定期購入のリスト
- 使っている電力・水道・ガス会社の名前
- いつも通っているスーパーやクリーニング店
こうした情報から書き始めることで、空欄を気にせず自然に続けられるようになります。
書きたくない項目を無理に書かないための工夫
エンディングノートには、書くのが難しいと感じる項目もあります。
たとえば、人間関係や気持ちの整理が関わる内容、判断がつかない将来のことなどです。
そんなときは、無理に埋めようとせず、「書かない選択」をしてもかまいません。
ここでは、書きたくない項目にどう向き合うか、その工夫をご紹介します。
書かない理由を簡単にメモしておくと家族が安心できる
項目を空欄にしたままでは、家族が「書き忘れ?」と不安に思うこともあります。
そこでおすすめなのが、なぜ書いていないのかを簡単にメモする方法です。
たとえば「まだ迷っているため未記入です」や「内容が気が進まないので記載を見送りました」といった短い一文で十分。
書くのがつらかったり、複雑な気持ちがあるときこそ、そのまま伝えておくことが家族へのやさしさになります。
私自身、「ここはまだ考えがまとまらないので空欄にしました」と一文だけ書いたページがありました。

書かない理由を書いておくことで、家族が「意図的に残した空欄だ」と理解してくれたのがありがたかったです。
「今は未記入」の一言を添えても十分伝わる
もっと気軽に進めたいときは、
「今は未記入」
「後日記入予定」
などの表現を添えるだけでもOKです。
この一言があるだけで、家族は「ここは今は考え中なのだな」と状況を把握できます。
特に、将来的に変わりそうな項目(希望する住まいやサービス、保管場所など)は、今決められなくても当然です。
だからこそ、あいまいなままでも伝える姿勢が、ノートの価値を高めてくれるのです。
- 今はまだ決めきれないため、空欄にしています
- 気持ちがまとまり次第、記入予定です
- 内容によっては、口頭で伝えるつもりです
このような補足があることで、家族が空欄に戸惑わずに済み、安心して読み進めることができます。
エンディングノートの空欄が家族に伝わる書き方のポイント
エンディングノートを家族が見たとき、「なぜ空欄なのか」がわかるように書いておくことがとても大切です。
ここでは、空欄に意味を持たせる工夫と、別紙で補足する場合の伝え方について解説します。
「未記入」「後日記載予定」など分かりやすい表記を使う
空欄があるページには、一言だけでも現状を伝える表現を入れておくと、家族が読みやすくなります。
たとえば、
- 「後日記載予定」
- 「今は記入せず」
- 「状況に応じて変更の可能性あり」
など、中立的な言葉を使うことで、重たい印象を避けることができます。
また、ページの端や枠外など、メインの記入欄以外に手書きで補足しておくのもよい方法です。
「意図的な空欄」だとわかるように書いておくことで、家族は不安にならず、前向きに読み進められます。

「今は保留にしています」とだけ書いたら、娘が「今考え中なんだね」と受け止めてくれて、変に心配させずにすみました。
重要情報を別紙にまとめた場合は保管場所を明記する
一部の情報をノートではなく別のメモやノートにまとめている場合、その旨と保管場所を明記しておくのが大事です。
ノートの該当ページに、
「この情報は別紙参照」
「○○の引き出しに保管」
といったメモを添えるだけで、情報がつながります。
たとえば、私はWi-Fiの情報やネットの設定メモを別のノートに書いていたので、「デジタルノートに記載済、引き出し左側に保管」と一言添えました。
そうすることで、ノートを見た家族が「ここに情報がある」と迷わずにすみます。
- この項目の詳細は青いノートに記入(寝室の引き出しに保管)
- Wi-Fiやネット設定は別冊のメモ帳に記載済です
- 書類の場所一覧は別紙A4にまとめています
このように、ノートと別紙を連動させることで、空欄も「意味ある空欄」として活かすことができます。
空欄を残しながらもエンディングノートを進める3つのコツ
エンディングノートをすべて埋めようとすると、どうしても途中で止まってしまいます。
でも、空欄を残したままでも前に進める方法を知っていれば、無理なく続けることができます。
ここでは、気負わずにエンディングノートを進めるための3つのコツをご紹介します。
一度で仕上げようとせず小さく書き始める
最初からすべて埋めようとすると、負担が大きく感じてしまいます。
そこで大切なのが、1項目だけ、1行だけという気軽な気持ちで始めることです。
たとえば、
「今日はWi-Fiパスワードだけ書く」
「冷蔵庫にいつも入れているものをメモする」
など、日常の延長線で取り組めばOK。
毎日書く必要もありませんし、思い出したときに少しずつ書くスタイルで十分です。

私は「紅茶を蒸らす3分のあいだに1項目だけ」と決めたことで、気づけば半分以上埋まっていました。
短時間で少しずつ進めるコツは、スケジュールの組み方でもっと楽になります。
その方法についてはこちらで解説しています。
苦手な項目を後回しにして続けやすくする
エンディングノートには、どうしても手が止まるような項目が出てきます。
そんなときは、そのページを飛ばして、書きやすいところから書くのがポイントです。
順番通りに書かなくてもいいと知っていれば、気持ちがラクになります。
「いずれ必要になるかも」と思う項目でも、今書けないなら一旦置いてOKです。
- 家族との関係性についての記述
- 思い出のエピソードやメッセージ
- 将来の希望に関する内容(住まいや暮らし方など)
書けるところから書くという柔軟さが、ノートを続けるコツになります。
注釈や別紙を使って情報を補う習慣をつける
空欄をそのままにしても、注釈や別紙で情報を補う習慣をつけておくと、あとから見直しやすくなります。
「ここは別紙に書いた」
「後日記入予定」
「詳細は別ノートに記載」
といった言葉を、各ページに添えるだけでも家族へのメッセージになります。
また、定期的にノートを開いて確認するクセをつけることで、思いついたときに書き足すことができるようになります。
ノートは一度書いたら終わりではなく、生活と一緒に変化していくものです。

「ここだけは書いておこう」と思ったことが別紙に残っていたおかげで、娘が「これで十分だよ」と言ってくれたのが印象に残っています。
実際の記入例を見ると、空欄を残しながらでも自然にまとまる形がわかります。
サンプルや書き方の工夫はこちらでご覧いただけます。
まとめ:空欄を恐れずエンディングノートを書けるところから始める
空欄のままでも、工夫次第で家族にしっかり伝わるエンディングノートが作れます。
ここでは、そのための実践的な方法をご紹介してきました。
飛ばした項目があっても工夫次第で家族に十分伝わる
苦手な項目や決めかねる内容は、無理に書かなくても問題ありません。
注釈や別紙を活用して、「あえて空欄にした理由」や「後から補足する予定」といった気持ちを伝えておけば、家族も混乱せずにすみます。
大切なのは、情報を完璧に埋めることではなく、伝えようとする姿勢です。
気負わず続けることがエンディングノート完成の近道
一気にすべてを書き上げようとせず、気になったときに、書けるところから。
「3分で1項目」や「週1で見直し」など、自分に合ったペースで書き進めていくことが、続けるコツです。
やがてそれが積み重なって、大切な暮らしの記録になります。
- 未記入の理由は一言メモで残す
- 別紙やカードで補足すればOK
- 続けられるペースを自分で決める
あなたの言葉やメモが、きっと家族の安心につながります。