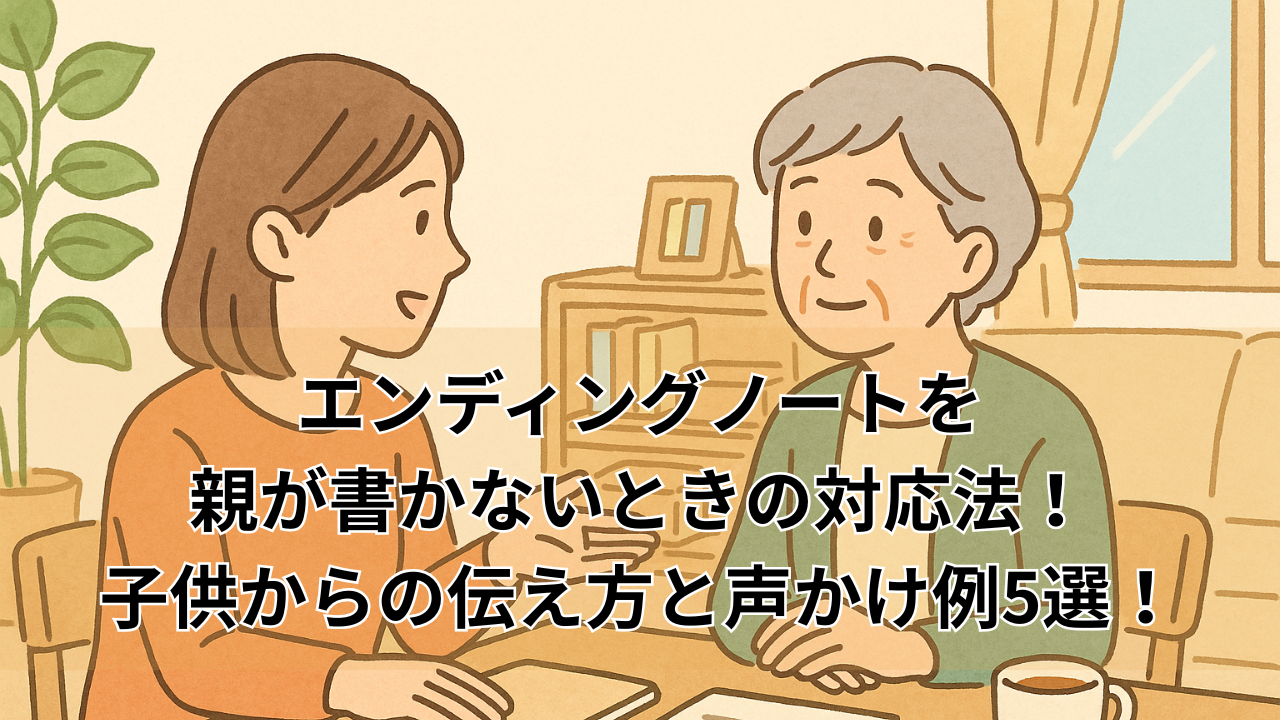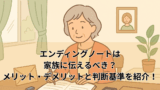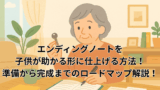「親にエンディングノートを書いてもらいたいけれど、どう切り出せばいいか分からない…」
そんな気持ちを抱える方は意外と多いのではないでしょうか。
「まだ元気だから必要ない」
「面倒そう」
と親に言われて、話を進めにくいこともありますよね。
そこでこの記事では、親が書かない理由に寄り添いながら、自然に気持ちを向けてもらえる関わり方を紹介しています。
少しずつ一緒に進めるための声かけ例や工夫を、実体験をもとにわかりやすくお届けします。
- 親がエンディングノートを書かない理由とその背景
- 押しつけずに促すための声かけ例
- 一緒に取り組むときのサポートの工夫
- 親に負担をかけずに進めるコツと注意点
エンディングノートを親が書かないときの基本対応と考え方
親にエンディングノートを書いてほしいと思っても、なかなか筆が進まないことはよくあります。
そのとき、無理に促すのではなく、まずは「なぜ書かないのか」を理解するところから始めることが大切です。
ここでは、親が書きたがらない背景を知ったうえで、安心して話を切り出すための基本的な考え方をお伝えします。
親が書きたがらない理由を理解する5つのポイント
エンディングノートを書かない親御さんの背景には、いくつかの共通した理由があります。
気持ちの整理がつかないことや、何を書けばよいかわからない不安があることも珍しくありません。
- 自分の老いを直視したくない気持ちがある
- 書く内容が難しいと感じている
- 急ぐ必要はないと思っている
- 子供に心配をかけたくないという遠慮
- 以前に専門的なノートに挫折した経験がある
このような理由を知らずに強く勧めてしまうと、かえって距離ができてしまうこともあります。

母も最初は「まだ元気だし、そんなの必要ないよ」と笑っていました。いきなり話すのではなく、きっかけ作りが大事だと感じました。
「家族のため」という目的を前向きに伝える方法
エンディングノートを書くことは、本人のためだけでなく家族のためでもあります。
ただ、「書いてほしい」と言うだけではなく、「子供が迷わず対応できるようにしておきたい」という目的を丁寧に伝えることで、親の受け止め方も変わってきます。
たとえば「私が何かあったときに、子供たちが困らないように」といった言い方は、親心に響くことが多いです。
「これはお願いじゃなくて、助けてほしいことなの」というスタンスも効果的です。
責めずに安心感を持たせる言い回しの工夫
「なんでまだ書いてないの?」という言い方では、親も構えてしまいます。
代わりに、「少しずつでいいから一緒に考えてみない?」や「わかる範囲だけメモしてくれたら助かるよ」といった柔らかい表現を使うと安心感が伝わります。
また、過去に自分がノートに挫折した体験を話すことで、「一緒にやる仲間」という雰囲気を作ることもできます。
親が書きたくなる空気を作るには、「責めずに寄り添う言葉」が一番のカギです。
特に年齢を重ねた親には、自尊心やプライドへの配慮がとても大切になります。
親にエンディングノートを書いてもらう具体的な声かけ例
いざ「書いてほしい」と伝えるとき、どんな言葉を選ぶかによって親の反応は大きく変わります。
ここでは、気持ちを逆なでしないよう配慮しつつ、前向きな気持ちで受け入れてもらえるような伝え方の工夫をご紹介します。
声のかけ方次第で、エンディングノートが“やらされごと”ではなく“家族のための優しさ”に変わります。
受け入れやすい前向きフレーズ5選
最初に伝える言葉は、なるべくポジティブな響きのあるものを選びましょう。
たとえば、「これ、メモ感覚で気軽に書いていいんだって」のように、気負わずに始められる印象を与えると効果的です。
- 「最近こういうの流行ってるらしいよ」
- 「暮らしのメモっていう感じでいいんだって」
- 「今のうちに書いておけば、あとで私たちが助かるよ」
- 「空欄あっても全然いいんだって」
- 「紅茶入れてる間に1行だけ書いてみようよ」
こうした言葉を使うことで、重たくなりがちな話題でも自然に切り出すことができます。

母に「最近こういうの流行ってるらしいよ」と言ったら、最初は笑ってましたが、「へぇ〜どんなの?」と興味を持ってくれました。
前向きなフレーズを知ったら、そもそもどこまで家族に伝えるかも整理しておくと安心です。
その判断の目安は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
親の不安を和らげる寄り添い型の伝え方事例3つ
「間違えたらどうしよう」
「書いたことで心配されるかも」
など、親自身が不安を抱えていることも多いです。
そんなときは、一緒に考えてあげる姿勢が心のハードルを下げてくれます。
以下のような言い回しは、安心感を伝える効果があります。
- 「あとで書き直してもいいみたいだよ」
- 「書けるところだけで十分なんだって」
- 「何かあっても私がちゃんと読めるようにしておいてくれると嬉しいな」
エンディングノートは完璧を目指すものではなく、“自分の暮らしの記録”として残すだけでも価値があります。
だからこそ、「今のままで大丈夫」「不安な部分はあとで一緒に考えよう」という伝え方が有効です。
「一緒にやってみよう」と促す言葉の使い方
ひとりで進めるのが不安な親には、「私も一緒にやるよ」という姿勢を見せるのが一番の安心材料になります。
特に、子供側も暮らしメモをつけていると伝えると、「それならやってみようかしら」と感じてもらいやすくなります。
たとえば「私もパスワードとか家のこと、ちょっとメモしてるんだ」と自分の例を出すのもひとつの方法です。
「一緒にやってみよう」は、親の背中をそっと押す最強のひとことです。
仲間意識があるだけで、気持ちが大きく変わることがありますよ。
親にエンディングノートを書いてもらうためのサポート手順
言葉だけではなかなか動いてもらえないときは、実際の行動でサポートしてあげるのが効果的です。
とくに最初の一歩を一緒に踏み出すことで、親の不安はぐっと小さくなります。
ここでは、親がエンディングノートに取り組みやすくなるような具体的なサポートの方法をご紹介します。
最初の1行を一緒に書き出してハードルを下げる方法
白紙のノートを前にすると、どこから書けばいいかわからず手が止まってしまいます。
そんなときは、一緒に1行だけでも書いてみることで、「なんだ、これでいいんだ」と思ってもらえます。
たとえば、「Wi-Fiパスワード:●●」など、日常の中の小さな情報から始めるのがおすすめです。
“始めること”が一番のハードルなので、それを一緒に乗り越える工夫が大切です。

私は紅茶を淹れている3分間に「ココアのえさの場所」とメモしたことがきっかけで、母が「あ、それ私も書こうかな」と言ってくれました。
空欄を残してOKにすることで安心感を与える
完璧に書こうとすると、かえってプレッシャーになってしまいます。
「空欄があってもいいよ」「あとで書けるから今は気楽にね」と伝えるだけで、ぐんと安心してもらえます。
- 「全部埋めなくていいんだって」
- 「必要なとこだけで助かるから」
- 「とりあえず書けるとこだけお願い」
空欄OKのルールがあるだけで、親はずいぶんと気が楽になるものです。
“間違えたらどうしよう”という気持ちをやわらげる、ちょっとした一言がカギになります。
短時間で進める小分けスタイルのサポート例
「1時間かけて書いて」と言われると気が重くなりますが、数分ずつであれば取り組みやすくなります。
「今日のお昼のあとに5分だけ」
「この項目だけやってみよう」
といった小分けのスタイルがおすすめです。
スケジュール帳や買い物リストのように、日常の延長線として扱うことで、取り組みやすさが格段に上がります。
親が疲れていないタイミングを見計らって声をかけるのもポイントです。
親に負担をかけないエンディングノートの進め方と失敗例
エンディングノートは、書く人の気持ちとペースに寄り添って進めることが何より大切です。
良かれと思っての声かけや手伝いが、かえって親にプレッシャーを与えてしまうこともあります。
ここでは、無理なく続けてもらうための関わり方と、ありがちな失敗例をご紹介します。
急がせない・重くしないための関わり方
「まだ書いてないの?」と聞いてしまうと、親は責められているように感じてしまいます。
その代わりに、「いつでもいいから、できるときでいいよ」といった余裕のある言い方を心がけましょう。
エンディングノートは一度で完成させるものではなく、少しずつ積み重ねていく暮らしの記録です。
気軽に書ける環境を整えるだけでも、親が自発的に進めるきっかけになります。

私は一度、「この週末に書こうよ」と言ってしまって、母に「そんな気分じゃない」と言われてしまいました。タイミングも大事ですね。
親のペースを尊重しながら進めるポイント5つ
親に安心してもらうには、子供側の接し方がカギになります。
次のようなポイントを意識することで、無理のないペースで進められるようになります。
- タイミングは親の体調や気分を見て選ぶ
- 無理に進めようとせず、自然に話題を振る
- 書いてくれたことに対して感謝の気持ちを伝える
- 書きたくなさそうな項目には無理に触れない
- 小さな進捗でも「助かるよ」と声をかける
このような工夫を重ねることで、親にとっても「続けられそう」と思える習慣になっていきます。
「完璧を求めない」姿勢が必要な理由とよくある失敗例
子供としては「きちんと全部書いておいてほしい」と思う気持ちもありますよね。
でも、それをストレートに伝えると、親のプレッシャーになってしまうことも。
「完璧じゃなくていい」という姿勢が、親にとって一番の安心材料になります。
ありがちな失敗として、「ちゃんと最後まで書いてね」と言ってしまったり、空欄を見て不満そうな顔をしてしまうケースがあります。
それよりも「ここだけでも書いてくれて助かったよ」と、できた部分を認める声かけが大切です。
完璧を求めないことは大切ですが、最終的に家族が助かる形に整える工夫もあります。
その流れやポイントは、こちらの記事で詳しく紹介しています。
まとめ:親がエンディングノートを書く気になる関わり方を実践する
エンディングノートを書いてもらうために必要なのは、「書かせること」ではなく、「一緒に考える姿勢」です。
親にとっても、押しつけられるより「思いやりを感じる声かけ」のほうが、ずっと行動につながりやすくなります。
ここまで紹介してきたポイントをもとに、あなたなりの関わり方を見つけていきましょう。
安心と感謝を伝える声かけが一番の説得材料
親がエンディングノートを書いてくれることは、家族にとって大きな安心につながります。
だからこそ、
「ありがとう」
「助かるよ」
という言葉を忘れずに伝えることが大切です。
「やってくれて当然」ではなく、「書いてくれるだけでありがたい」という気持ちが、親のやる気を引き出します。
最初の1行だけでも、書いてくれたことにしっかり感謝の気持ちを伝えてください。

母が「冷蔵庫のリストだけ書いておいたよ」と言ってくれたとき、「それだけでも十分助かる!」と声に出して伝えました。親も嬉しそうでした。
一緒に取り組む姿勢が親子の信頼関係を深める
エンディングノートは、ただの情報整理ではありません。
親子で未来のことを一緒に考える、コミュニケーションのきっかけでもあります。
「自分のことは自分で考える時期だから」と親に任せきりにするのではなく、一緒に考える時間をつくることが大切です。
「私も書いてるから、一緒にやってみよう」という一言から、親子の関係が変わるかもしれません。
そしてその時間が、きっとお互いの安心感にもつながっていきます。