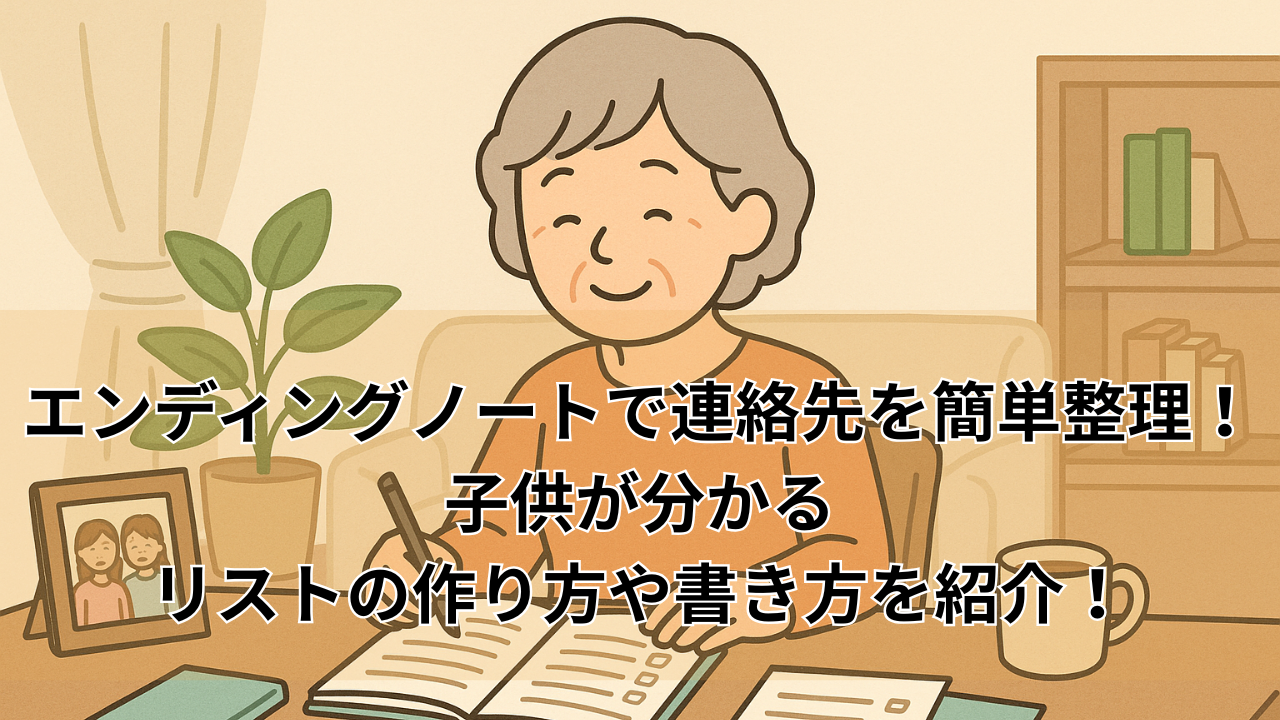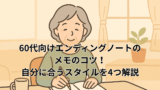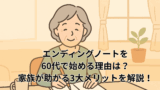「親の連絡先って、どこに何があるの?」
これは、私の娘がふと漏らしたひとことです。
電話帳に登録していても、いざという時に「誰に・どんな順番で連絡すべきか」は分かりづらいもの。
特に親戚や昔の知人など、家族にとって“知らない関係”は、連絡が後回しになってしまうこともあります。
だからこそ、エンディングノートに「連絡先リスト」としてまとめておくと、子供の安心につながります。
この記事では、自分も家族も見やすくて続けやすい連絡先リストの作り方をわかりやすくご紹介します。
- 連絡先リストをエンディングノートに書く基本の考え方
- 誰から書くか迷わない優先順位の決め方
- 見やすく使いやすいリスト作成の3ステップ
- 家族と安心を共有するための保管・伝え方のコツ
連絡先リストをエンディングノートに書く基本の考え方
「電話帳に入ってるから大丈夫」と思っていても、いざという時に家族が見つけられるとは限りません。
スマホを開けなかったり、連絡の優先順位が分からなかったりするだけで、家族は大きく迷ってしまいます。
だからこそエンディングノートに連絡先リストを残しておくと、子供にとっての安心につながるのです。
とはいえ、いきなり全員分を書き出す必要はありません。
必要な人から少しずつ整理していけばOKです。
全員を書き出そうとせず優先度の高い人から整理する
私が最初に書いたのは、娘に「この人にだけは先に知らせて」と伝えたかった人たちだけでした。
大切なのは“全部書くこと”ではなく、“誰にまず伝えるか”をはっきりさせることです。
親戚や近くの友人など、家族にとって知らない相手ほど早くリストに入れておくと安心です。

私は母の友人関係がよく分からず困った経験があったので、「私も同じことを娘にさせたくない」と思って書き始めました。
家族が見やすいシンプルな形にまとめる
名前・関係性・連絡手段(電話やLINEなど)を1行で書くスタイルがおすすめです。
書式にこだわらず、見てすぐ分かる・伝えられることが何より大切です。
「○○さん(父の妹)/固定電話/必要なときだけ連絡して大丈夫」など、簡単な補足をつけるだけでも家族は迷いません。
- まずは“家族が知らないけど大事な人”を優先して書く
- フルネームでなくてもOK。わかる範囲で大丈夫
- あとで増やすことを前提に、気軽にスタート
自分が「伝えておきたい」と思う相手から、気楽に書いていきましょう。
家族が見やすいシンプルな形にまとめる。自分に合った書き方スタイルを知りたい方はこちらもご覧ください。
連絡先リストに入れるべき項目と優先順位の決め方
連絡先を書こうとすると、「この人も…あの人も…」とつい増えてしまいがちです。
でも、いざという時に必要なのは“すぐ連絡すべき相手”から順に絞り込まれたリストです。
子供や家族が「誰に連絡すればいいのか」を迷わず判断できるように、優先順位をつけて書くのがポイントです。
1. 家族や子供がすぐに連絡できる親戚やキーパーソン
まずリストに入れておきたいのは、親戚や昔からの付き合いがある人など、家族が知らないけれど大切な人たちです。
たとえば
「妹(○○子)/○○県在住/電話番号」
「長年の知人(○○さん)/お世話になった方」
といったように、名前と簡単な関係性を添えると伝わりやすくなります。
関係性をひとこと添えておくだけで、子供が状況をイメージしやすくなります。

私は「母のいとこ」にあたる人が数人いて、名前だけだと娘がピンとこないと思ったので「親戚の中で一番連絡が早い人」など説明も添えました。
2. 親しい友人や近隣で助けてもらえる人
近くに住んでいる友人やご近所さんは、緊急時に頼れる存在です。
私は、「○○さん(お隣の奥さん)/困ったときいつも助けてくれる」とメモしています。
普段の会話の中では当たり前のように話している人でも、家族からすれば“知らない人”というケースが多いものです。
付き合いの深さや関係性を軽く補足するだけで、連絡の必要性が分かりやすくなります。
3. 地域コミュニティや趣味仲間など必要に応じた連絡先
習い事の先生や、趣味サークルのメンバーなど、日常の中で関わりが深い人たちも忘れずにリストに入れたいですね。
私は
- バイオリンの先生
- ガーデニング仲間
など、グループ名だけでも残しておくようにしています。
内容によっては、家族が本人に連絡せずとも“つながり”だけ分かっていれば助かることもあります。
優先順位のヒント
| 分類 | 具体例とポイント |
|---|---|
| 親戚・キーパーソン | 続柄や関係性も一緒にメモする |
| ご近所・親しい友人 | 家族にとって未知の相手を優先 |
| 地域・趣味つながり | グループ名・役割だけでもOK |
「娘が知らないけれど大事な人」を優先に、ひとつずつ丁寧に書いていけば自然と形になります。
使いやすい連絡先リストを作る3つの手順
連絡先リストを作るときは、「書き方」よりも「伝わりやすさ」が大事です。
誰にでもすぐ伝わるようなシンプルな手順で書いていけば、続けやすく、見やすいリストになります。
ここでは、実際に私がやっている簡単な3ステップをご紹介します。
1. 名前と関係性をセットで書く
名前だけでは、家族が「この人は誰?」と迷ってしまうこともあります。
「○○さん(学生時代の親友)」
「○○さん(昔の職場の同僚)」
など、関係性を短く添えるのがポイントです。
関係性を書くことで、「連絡すべきかどうか」の判断がしやすくなります。

私は一度「○○さん」とだけ書いたら、娘に「この人、どの○○さん?」と聞かれてしまって……それ以来、ひとこと説明を添えるようにしています。
2. 電話番号やメールアドレスを最新の情報にする
連絡先の番号やメールは、古いままだと逆に混乱のもとになります。
使わなくなった連絡先や、変更になったものはこの機会に見直してみましょう。
私は定期的にスマホのアドレス帳と照らし合わせて、「今も使っているかどうか」で整理しています。
連絡方法が複数ある場合は、「まずは電話、つながらなければLINE」と補足するのもおすすめです。
3. 紙やスマホメモなど自分が管理しやすい形式を選ぶ
リストの形式は、自分が「無理なく続けられるかどうか」が大切です。
私はA5サイズのノートに1ページずつカテゴリ分けして書いていますが、スマホのメモ帳に書いてもOKです。
形式にこだわらず、「手に取りやすい」「書き直しやすい」ものを選ぶことが長続きのコツです。
- 名前と関係性をセットで書く
- 最新の連絡先を確認して反映する
- 自分が続けやすい形式で管理する
この3ステップなら、負担なく書き進められて、家族にもやさしいリストが自然と出来上がりますよ。
連絡先リストを家族と共有して安心につなげる工夫
せっかく作った連絡先リストも、家族が見られなければ意味がありません。
大切なのは「いつでも家族が見つけられる場所にあること」そして「最新の状態に保つこと」です。
内容をすべて共有しなくても、リストの存在と保管場所だけ伝えておくだけで、家族の安心感はぐっと高まります。
保管場所を決めて家族がすぐ見つけられる状態にする
私は、リビングの棚にあるファイルに「連絡先メモあります」と書いて貼っています。
中身を細かく見せる必要はなく、「いざという時はここを開いてね」とだけ伝えておけば十分です。
家族にとっては「どこを見ればいいか」が分かっているだけで安心につながります。

娘に「何かあったらここ見ればいいんだよね」と言われて、伝えておいてよかったと思いました。
娘や息子と一緒に見直して最新の状態を保つ
連絡先は変わることも多いので、定期的に見直すことが大切です。
私は季節の変わり目などに、「この番号、今も使ってる?」と娘と一緒に確認する時間をつくっています。
共有というより“一緒に管理する”という感覚にすると、家族も自然と関心を持ってくれます。
- リストの場所をメモや付せんで分かりやすくする
- 全部見せる必要はなく「必要なときに見る」形でもOK
- 定期的に見直すきっかけをつくって、無理なく更新
リストを通して家族とやりとりする時間が、「備え」を少しずつ自然なものにしてくれますよ。
連絡先リストがないと子供が困る理由
「いざというとき、どうすればいいのか分からなかった」
これは、母を見送った友人が口にした言葉です。
連絡先がまとまっていないと、子供は最初の一歩でつまずいてしまうことが多いのです。
どこに何があるか分からない状況では、焦りや不安が重なって、行動が遅れてしまうことも……。
緊急時に誰に連絡すべきか分からず時間がかかる
私の娘も、以前こんなふうに言っていました。
「親戚やお母さんの知り合いって、私ほとんど分からないんだよね」と。
電話番号だけ書いてあっても、その人がどんな人で、どの順番で連絡するべきか分からないと、かえって戸惑わせてしまうかもしれません。
「まずこの人」「次にこの人」と優先順をつけることで、子供が落ち着いて行動できるようになります。

私は番号だけでなく、「この人には後からでも大丈夫」「この人はすぐに知らせて」と補足メモを添えています。
親戚や友人の情報が散乱していると家族が混乱する
スマホ、手帳、冷蔵庫のメモ……連絡先があちこちに点在していると、家族はそれを探すだけで一苦労です。
私も以前、メモ帳に書いた電話番号を探して娘に「あれ?見当たらない!」と慌ててしまった経験があります。
だからこそ、1カ所にまとめておくことで、家族が迷わず必要な連絡ができるようになります。
“探さなくていい”というのは、家族にとって何よりの思いやりになります。
- 誰に連絡すればいいか分からず対応が遅れる
- 親戚・友人の情報を探すのに時間がかかる
- 順番や関係性が分からず判断に迷う
完璧じゃなくていいから、“家族がすぐ動けるヒント”になるリストを残しておきましょう。
まとめ:連絡先リストは子供が迷わず動ける安心の仕組みになる
連絡先リストは、ただの情報のメモではありません。
子供が「迷わず動ける」「安心して行動できる」ための、心の支えになる仕組みです。
ほんの数人でも、「誰に、どう連絡すればいいか」が分かるだけで、家族の不安は大きく減らせます。
優先度の高い相手から整理して書き始めるのがポイント
全部を完璧にまとめようとする必要はありません。
まずは「この人にだけは先に知らせたい」と思う人から、ゆるやかに書き始めるのが一番です。
「娘には話してないけれど、大切な人」は意外と多いもの。
そうした“見えないつながり”を、少しずつ目に見える形にしていきましょう。

私は「お隣の奥さん」「昔の職場の友人」など、身近だけど娘が知らない人を中心に書いています。
優先度の高い相手から整理して書き始めるのがポイント。全体で取り組むと得られる安心感についてはこちらで詳しく解説しています。
空欄があってもいいという気持ちで始めると続けやすい
「書けるところから、できたぶんだけ」
それが続けられるコツですし、家族にとっても意味のある情報になります。
たとえ途中でも、連絡先が3つ書いてあれば、それはもう立派な“伝える準備”です。
エンディングノートは完成させるためのものではなく、“伝わること”を目的にすればいいんです。
- まずは「家族が知らないけど大事な人」から書く
- 空欄OK・途中OKで気軽に書き始める
- 伝わることを第一に、無理せず少しずつ整える
誰かに伝える準備は、自分の暮らしを見つめ直すやさしい時間でもあります。
あなたらしい連絡先リストが、家族にとって大きな支えになりますように。