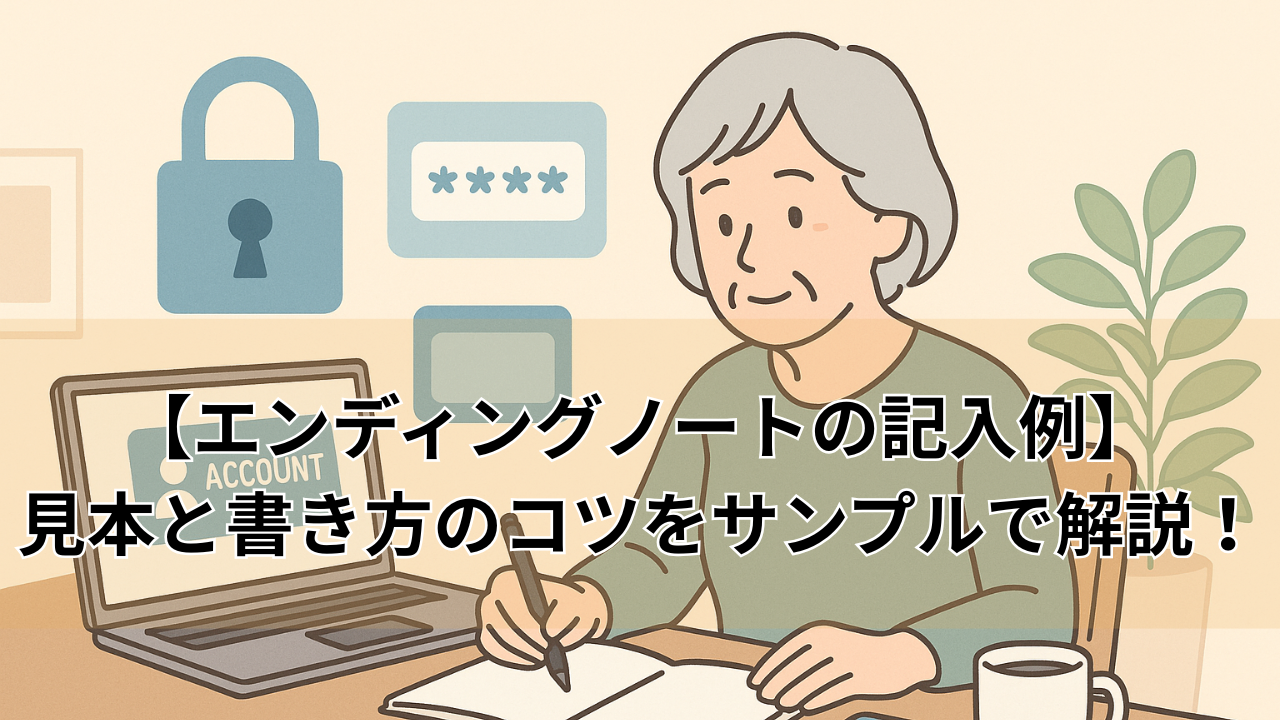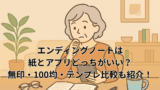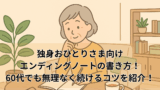エンディングノートに興味はあるけれど、「何を書けばいいのか分からない」という声は少なくありません。
そんなときは、記入例や完成した見本を参考にするのがおすすめです。
内容を丸ごと真似しなくても、「自分ならこう書こうかな」と具体的なイメージが湧いてきます。
60代から始める終活の第一歩として、まずは1行から気軽に書けるようになるヒントを見つけてみませんか?
- エンディングノートの見本や記入例の活用方法
- 60代からでも書き始めやすいステップ
- 家族が助かる情報の具体例と整理のコツ
- 自分用にアレンジするための書き方アイデア
エンディングノートの見本や記入例を参考にすると書きやすくなる
エンディングノートを書こうと思っても、白紙のページにいきなり向き合うのは難しいものです。
「何から書けばいいの?」
「この書き方で合ってる?」
と不安になる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに心強いのが、記入済みの見本やサンプルです。
記入例があると、具体的なイメージが湧きやすくなり、最初の一歩をスムーズに踏み出せます。
具体的な見本やサンプルがあると60代でも進めやすい
エンディングノートには正解がないぶん、自由すぎて書きづらいと感じる方もいらっしゃいます。
でも、実際の記入例を目にすることで「こう書けばいいんだな」と安心できることがあります。
たとえば、以下のような暮らしに直結した情報の記入例があると、自分の生活に当てはめやすくなります。
- Wi-Fiパスワードと契約会社
- 銀行口座名と使っている用途
- ペットの好きな食べ物や病院名
白紙に1から考えるのではなく、例をヒントにしながら書けることで、気軽に始められるようになります。

私は「完璧に書かないと」と思い込んで動けなかったのですが、記入例を見たことで「これでいいんだ」と安心して手が動きました。
子供が助かった実例から必要な情報が分かる
実際に「書いてあって助かった」という声からは、家族が本当に困る場面が見えてきます。
たとえば、ゴミ出しの曜日が分からず困った、家電の保証書がどこにあるか分からなかった、というような小さなエピソード。
これらを元に記入しておくと、「家族が読んだときに助かる情報」を残す意識が自然と芽生えます。
- ゴミ出しの曜日と分別ルール
- エアコンのリモコンの場所や型番
- 常備薬の保管場所と飲み方のメモ
こうしたリアルな情報を見本から得ることで、自分の生活に合った記入項目が見えてきます。
「何を書けばいいか分からない」状態を防ぐために、実例を活用するのはとても効果的です。
エンディングノートの見本を活用することで得られる効果
エンディングノートの見本や記入例を活用すると、「何を書けばいいか」が見えてくるだけでなく、家族への伝わり方も大きく変わります。
見本を参考にして整理されたノートは、読み手にとって分かりやすく、実際に役立つ1冊になります。
ここでは、見本を活用することで得られる具体的な効果についてご紹介します。
空欄が多いと家族が迷いやすくなる現実を防げる
エンディングノートは書いた本人にとっては「途中まででもよし」ですが、読む側の家族にとっては違います。
空欄が多いほど、何が分かっていて何が分かっていないのかが曖昧になり、結果として迷いを生んでしまうのです。
たとえば、複数ある通帳のうち、どれが現役で使っているものなのか、書かれていないと判断が難しくなります。
そこで見本を参考にすることで、「この情報は書いておいたほうがいい」という気づきが得られ、必要な情報の抜けを防げます。

私は母のノートに空欄が多かったとき、「結局どれを信じて動けばいいの?」と不安になりました。
完成例を見て暮らし情報を整理する重要性が分かる
エンディングノートに必要な情報は、日常生活の中に散らばっていることが多いものです。
完成例を見て、「このくらいの粒度で書けばいいんだな」とイメージできると、身の回りの情報も整理しやすくなります。
特に参考になるのは、名前だけでなく理由や補足がある例です。
たとえば
「A銀行:年金受取用」
「〇〇病院:風邪のときにいつも行く」
といったメモがあれば、家族が後から見たときも判断がしやすくなります。
- 「〇〇銀行(生活費用)」と用途まで書く
- 「〇〇医院(内科・風邪のとき)」と診療科も記載
- 「冷蔵庫の上の引き出しに印鑑」と具体的な場所を書く
暮らし情報はほんの一言の補足があるだけで、読み手にとっての分かりやすさが大きく変わります。
エンディングノートの見本や記入例を活用する3つの手順
「見本はあるけれど、どうやって活用すればいいの?」という方に向けて、無理なく書き進める3つの手順をご紹介します。
一気に仕上げようとせず、見本をヒントに段階的に進めていくことが続けるコツです。
このステップを踏むことで、自分の生活に合った暮らしメモが自然と出来上がっていきます。
書きやすいフォーマットを選び基本情報から埋める
まずは、見本を見ながら自分に合ったフォーマットを選びましょう。
エンディングノートには、冊子型・PDF・アプリ形式などさまざまなスタイルがあります。
紙の方が落ち着く方もいれば、スマホで手軽に入力したい方もいます。
選び方のポイントは、
「書きやすそう」
「続けられそう」
と思えるものを選ぶこと。
最初に埋めるなら、名前・生年月日・住所・連絡先など、すぐに書ける基本情報からがおすすめです。

私はPDFを印刷して、まず「冷蔵庫のメモに書いてあること」から転記するところから始めました。
紙にするかアプリにするかで、書きやすさや続けやすさは変わります。
それぞれの特徴や選び方をこちらでご紹介しています。
子供や家族が必要な暮らし情報を優先して記入する
次に記入したいのが、「自分のため」ではなく「家族のため」に残したい情報です。
見本を見ると、「こんな項目まであるのか」と気づくことがよくあります。
たとえば以下のような項目です。
- Wi-Fiパスワードと通信会社名
- ゴミ出しの曜日と出し方のルール
- ペットのごはん・病院情報
- 通っている美容院・かかりつけ店の連絡先
自分では当たり前すぎて忘れていた情報も、家族にとっては「知っておいてほしい情報」になります。
実例を参考に自分の状況に合わせて追加項目を決める
最後に、見本をそのまま使うのではなく、自分の暮らしに合わせてアレンジすることが大切です。
たとえば、「家の中で迷いそうな場所」や「こだわっている習慣」など、個別の情報を追加してみましょう。
私の場合は、
「毎朝やっている体操のメニュー」
「炊飯器の使い方メモ」
などを書き足しました。
見本にはないけれど、「あったら役立ちそう」と思ったことを自由にメモしていくと、より実用的になります。

母が残してくれた「洗濯機の柔軟剤は少なめに」が、何だか嬉しくて、私もそんな一言を残したくなりました。
エンディングノートの書き方サンプルを自分用にアレンジするコツ
見本や記入例をそのまま写すだけでは、自分の暮らしにぴったりのノートにはなりません。
エンディングノートは「自分と家族に合った形」にアレンジすることで、ぐっと実用的になります。
ここでは、見本を参考にしつつ、自分らしい1冊にするためのアレンジのコツをご紹介します。
無理にすべて真似せず必要な部分だけ取り入れる
見本やテンプレートを見ていると、「全部埋めなきゃ」と思ってしまいがちですが、それは必要ありません。
自分に関係のない項目は書かなくて大丈夫ですし、書けない部分は空欄でも問題ありません。
たとえば「介護についての希望」など、今はまだ考えられない項目があるなら、後回しにしておくのもひとつの方法です。
逆に「よく聞かれるWi-Fiの情報だけでも先に書いておく」など、できるところだけ真似して埋めていくと気軽に続けられます。

私は「全部書かなきゃ」と思っていたときは手が止まりがちでしたが、娘に「Wi-Fiだけで十分助かるよ」と言われてから気が楽になりました。
自分の暮らしに合わせて、無理なく続ける工夫もあります。
そのヒントをこちらでご紹介しています。
家族が迷わないように注釈や補足を加える
たとえば「〇〇銀行」とだけ書いてあるよりも、「〇〇銀行(生活費用の振込口座)」と書いてあるほうが、家族は状況を把握しやすくなります。
見本を参考にするだけでなく、「家族が見て分かるように説明する」気持ちで補足を加えると、安心感が大きくなります。
また、場所の記載も「2階のタンス」だけでなく、「2階のタンスの右から2段目」など、具体的な位置まで書いておくと迷いません。
さらに「これはよく使っていた」「これは処分していい」など、思い出や判断のヒントも一言添えるのもおすすめです。
- 「〇〇病院(風邪のときによく行っていた)」
- 「この棚の一番奥に通帳あり(毎月確認していたもの)」
- 「冷蔵庫の下段・左奥に梅干し(自分で漬けた分、味濃いめ)」
こんなふうに、ちょっとした補足があるだけで、読み手の安心につながります。
まとめ:エンディングノートは見本を参考に小さく始めるのが続けるコツ
ここまで、エンディングノートを見本や記入例とともに書き進める方法をご紹介してきました。
一番大切なのは、完璧を目指さず「できるところから小さく始める」ことです。
完成させようとするのではなく、「まず1行」書ければ大成功です。
記入例や完成例を見ると具体的なイメージが湧く
何を書けばいいか分からないときこそ、他の人の記入例や完成したノートがヒントになります。
「この程度でいいんだ」
「こんな風に書けばいいんだ」
と、気持ちが軽くなる効果があります。
特に、60代の方にとっては、実用的なサンプルを見ることで、「自分にもできそう」と思えるようになります。
情報をまるごと真似するのではなく、形式や流れを参考にして、自分に合った形に整えていくのがコツです。

完成例を見てからは、ノートを「書かなきゃ」ではなく「書いておこうかな」と思えるようになりました。
子供が助かった実例を参考に暮らし情報を残す
暮らしメモとしてエンディングノートを活用するなら、家族が見てすぐ分かる情報を意識することが大切です。
たとえば、料理に使う調味料の銘柄、よく行くスーパー、冷凍庫に入れておいた手作りの保存食など。
こうした日常の些細な情報が、家族にとっては「どこを見ればいいか分かる」「探さなくて済む」という安心につながります。
そのためにも、身近な実例をヒントに、自分の生活に置き換えて書くことを意識してみてください。
- ガスの元栓の位置と止め方
- 掃除機の紙パックの替えがある場所
- コープの注文方法と配達曜日
エンディングノートという名前に気後れせず、「暮らしメモ」として軽やかに書いていけると続けやすくなります。